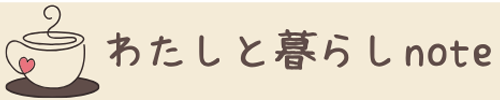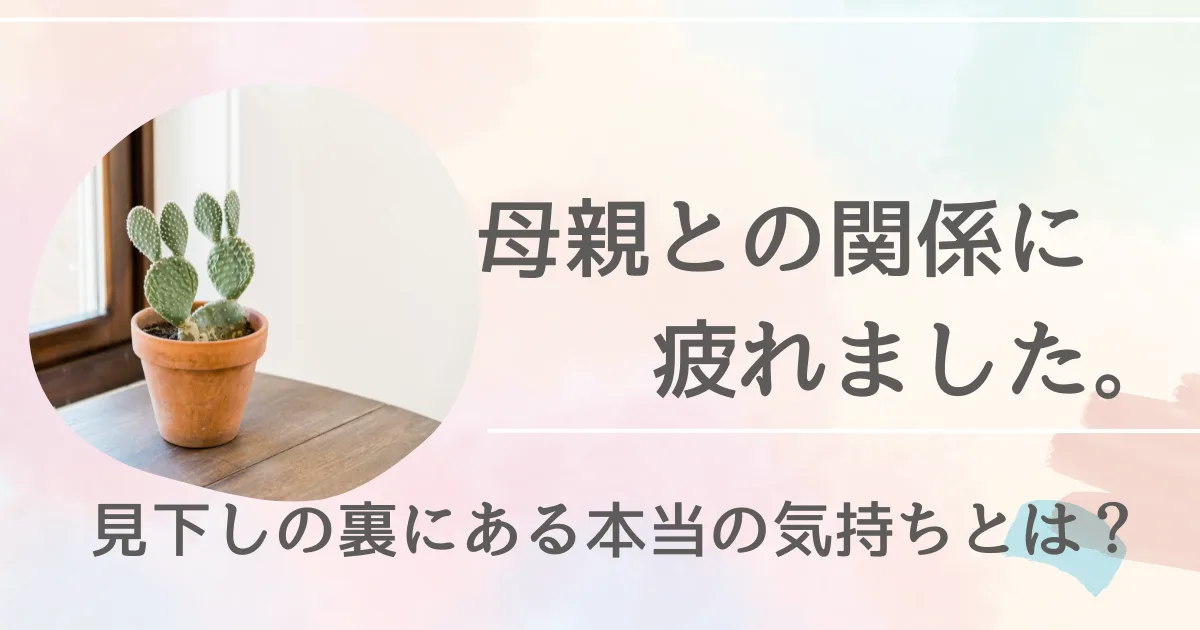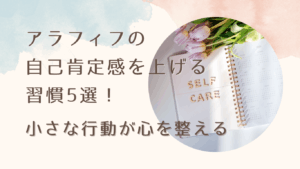「母親にイライラしてしまう」「つい上から目線で見てしまう自分が嫌」
そんな気持ちに、心が疲れてしまっていませんか?
40代・50代になると、自分の人生と母の生き方を比べる機会が増えます。
若い頃は気づかなかった違和感や価値観のズレが浮かび上がり、「なんでこうなの?」と感じてしまうこともあるでしょう。
でも、見下すような感情の奥には、「本当は分かってほしい」「もっと優しく接したい」という願いが隠れていることも多いのです。
この記事では、母親を見下してしまう気持ちの裏側にある心理と、心を少しずつラクにしていくためのヒントをお届けします。
- 母親を見下してしまう気持ちの正体と、その裏にある本当の心理
- イライラやモヤモヤが生まれる理由と、心が疲れてしまう背景
- アラフィフ世代が抱えやすい「母との距離の悩み」をラクにする考え方
- 母を「母親」ではなく「ひとりの人」として見られるようになるヒント
- 母への感情をやわらげ、関係を穏やかに整えていくための小さな習慣
自分を責めるのではなく、優しく整えていくための一歩として読んでみてください。
母との関係に疲れてしまうのはなぜ?

私は、母からのLINEが来るのが、怖いと思う時期がありました。
両親は、弟家族と2世帯で住んでいますが、弟家族は「え?」という出来事に見舞われることが多いのです。俯瞰して見るとまるでドラマを観てるような感じ・・・
両親はいつもため息ばかりついていて、会えば心配事を聞かせる。心配事の相談ならいいのだけど、多くは弟、嫁、孫たちへの愚痴がほとんど。
実家から自宅に帰ったあとはグッタリ疲れてしまう。
そしてLINEが何通も続く・・・
愚痴を聞きたくないと言ったら、「こんなこと話せるのは、〇〇(私)しかいないから」と言われる。これは呪いだと思います。
母はスッキリするかもだけど、聞かされた方はモヤモヤが積もるだけなのに。
私と同じように、母親の愚痴を聞きたくないと思っている人は多いのではないでしょうか?
特に「母親」だから聞きたくないというのがあると思うのです。
大人になって見える「母の弱さ」と「違和感」
40代・50代になると、母親をひとりの大人として客観的に見る機会が増えますよね。
そのとき、若い頃は気づかなかった「母の弱さ」や「考え方の違い」に戸惑う人も多いのではないでしょうか?
「なんでそんなこと言うの?」「もっとこうすればいいのに」
そう感じるたびに、心の中に小さなモヤモヤが積もっていきます・・・。
アラフィフ世代に多い「親子の立場の変化」
人生経験を積んだ今、私たちは「母を助ける側」に立つことが増えています。しかし、母はいつまでも「自分が親である」という立場を崩したくない。
この微妙なバランスのズレが、気づかぬうちにストレスを生むことになるのでしょう。
「母だからこそ分かってほしい」という期待の裏側
「母親なんだから、私の気持ちを分かってくれるはず」
そんな期待が裏切られると、悲しみや苛立ちに変わり、見下しの感情として表に出ることに。
でも実はその気持ちの奥に、「本当はもっと分かり合いたい」という願いが隠れているのだと思います。
母を見下してしまう気持ちの正体

母親を見下してしまう気持ちは、単なる「高慢さ」や「冷たさ」ではありません。
その根っこには、誰もが抱えている「理解されなかった悲しみ」や「価値観のズレからくる寂しさ」が隠れている。
「理解されなかった悲しみ」と聞いて、思い当たることありませんか? 私は、「親にとっていい子ではなかった」との思いが強かったので、たくさんの「理解されなかった」という思いがありました。
「理解されなかった悲しみ」が怒りに変わる
母に言いたいことを我慢してきた人ほど、心の奥には「理解されなかった悲しみ」が溜まっています。
自分では気づいていなかった小さな出来事でさえも、潜在意識では覚えているのです。
それが表面では怒りやイライラとして現れ、「なんで分からないの?」という気持ちに変化します。
「自立した自分」と「変わらない母」とのギャップ
社会の中で自立してきた私たちは、自分の価値観で物事を判断するようになります。
一方、母は昔のままの価値観や生活リズムを大切にしていることが多い。そのギャップが、「もう少し柔軟になればいいのに」という見下しにつながることもあります。
見下しは「本音を守るための防衛反応」
実は、母を見下す気持ちは「自分を守るための防衛反応」でもあります。傷つきたくない、分かってもらえなかった悲しさを感じたくない・・・
そんな心の防御が、無意識に母を下に見てしまう形で表れていると思います。
母を「母親」ではなく「ひとりの人」として見る

母を見下してしまう気持ちがあるとき、私たちは無意識のうちに「母親とはこうあるべき」という理想像を抱いています。
けれども、その「母親像」は、もしかしたら私たちが子どもの頃に思い描いた「何でも分かってくれる存在」「強くて優しい存在」なのかもしれません。
完璧な母を求めないという選択
「母親だからこうあるべき」という理想像を手放すと、関係は少しラクになります。
母も私たちと同じように、不器用で、迷いながら生きてきたひとりの人。完璧さを求めるのをやめると、過剰なイライラや落胆が減っていきます。
母の人生にも背景があると想像してみる
母がなぜ今のような言動をするのかには、必ず「その人なりの理由」があります。
育った時代、環境、家庭の中での経験
それらを少し想像してみるだけで、母への見方が柔らかくなります。
「母もまた不器用に生きてきた」と思えたとき
母が完璧でないように、私たちも完璧ではありません。
そのことを認められたとき、母への見下しは少しずつ溶けていき、「いろいろあったけど、まぁいいか」と思える瞬間が訪れました。
気持ちをラクにするためにできること

母との関係で心が疲れているとき、「もっと優しくしなきゃ」「見下しちゃいけない」と自分を責めてしまいがちです。
でも、無理をして変わろうとすると、かえって心がすり減ってしまいます。
大切なのは、「関係を良くすること」ではなく、「自分の心をラクにすること」。
そのためにできる小さな工夫を、少しずつ取り入れてみましょう。
距離を調整して、無理のない関係をつくる
一緒にいる時間が長いと、小さな違和感が積み重なります。
あえて会話を減らしたり、会う頻度を少し減らすのも悪いことではありません。
「少し距離をとる勇気」が、心を守る第一歩です。
母の「すごいところ」をひとつ探す
イライラしたときほど、母の「良いところ探し」をしてみましょう。
家族を支えてきた努力、料理を続けてきた忍耐、近所づきあいの丁寧さなど。
小さな尊重を積み重ねることで、心が少しずつやわらぎます。
「ありがとう」を小さく積み重ねてみる
「ありがとう」を一言伝えるだけでも、関係は少しずつ変わります。
最初はぎこちなくても大丈夫。感謝を「習慣」にすることで、母を見る目が自然と優しくなれるとおもいますよ。
自分を癒すことで、母との関係も変わっていく
母との関係を見直すとき、多くの人がまず「母を変えよう」としたり、「自分が我慢しよう」と思ってしまいます。
けれども本当に大切なのは、母を変えることではなく、自分の心を整えること。
自分の心が穏やかになれば、母との関係も自然にやわらかく変わっていきます。
「見下してしまう自分」を責めない
母を見下してしまう自分を責める必要はありません。その感情は、心が疲れているサインです。
まずは「そう感じてしまう自分を許す」ところから始めてみましょう。
自分の心を満たすことが、母への優しさにつながる
自分が満たされていないときほど、他人に厳しくなりがちです。心を整える時間を持つこと、好きなことをする時間を大切にすること。
それが、母との関係にも自然な優しさをもたらすのだと思います。
「完璧な親子」ではなく「心が穏やかな関係」を目指して
理想の親子関係を求めすぎず、「ちょうどいい距離で心地よく」が目標で大丈夫。
無理に仲良くする必要も、過去をすべて許す必要もありません。「お互いに楽でいられる関係」を目指すことが、最も現実的で幸せな形だと思います。
まとめ|母への見下しの裏にある「本当の思い」に気づこう
母を見下してしまう気持ちは、誰にでも起こりうる自然な感情です。
それは決して冷たさや傲慢さではなく、「分かってほしい」「受け入れてほしい」という心の奥の願いが形を変えたもの。
つまり、「愛されたい」という思いの裏返しなのでしょうね。
母に対して感じる苛立ちや見下しは、自分の中の繊細な心が発しているサイン。
無理に押し殺したり、罪悪感を持たなくてもいい。「そう感じてしまうのも、今の私」と認めることで、心は少しずつ落ち着いていきます。
そして、母を「母親」という立場ではなく、「ひとりの人間」として見てみると、これまで見えていなかった背景や努力、そして「この人も懸命に生きてきたんだな」と理解すること。
完璧を目指さなくても、仲良くしようと無理をしない。大切なのは、自分の心が穏やかでいられること。
母との関係を変えようとするよりも、自分を癒すこと、自分を大切にすることが、結果的に母への優しさにもつながります。
母への見下しの裏にある「本当の思い」に気づいたとき、自分の中で長く固まっていた感情が少しずつ緩むのでしょう。
その気づきこそが、母との関係を変えて、そして何より、自身を自由にしていく一歩になるのだと思います。